
| タイトル | 淳和天皇勅願所古跡 |
| 作者 | 不明 |
| 設置場所 | 横浜市神奈川区 吉祥山茅草院慶運寺 |
この石碑は、かつて「浦島寺」と呼ばれた観福寿寺にあったもの。1867年の神奈川大火により観福寿寺が途絶えたためこの慶運寺に移設された。浦島太郎は雄略天皇の478年に龍宮へ行き、淳和天皇の825年に故郷に帰ってきたとされている。太郎の父・浦島太夫はもともと相模国三浦の生まれだが、丹波に赴任していた時に太郎は生まれた。太郎は丹波から龍宮寺に行ったのだが、347年後に丹波に帰り着いた時には両親はすでにいなかったという。観音様のお告げで太郎は神奈川に両親の墓があることを知り、神奈川にたどり着く。この石碑は淳和天皇の勅願所の跡の記念。天皇の勅命で浦島太郎を祀る場所を設けたということだろう。横浜市の地域有形民俗文化財に指定されている。
説明板は次の通り
横浜市地域有形民俗文化財
浦島太郎伝説関係資料
平成7年11月1日登録
所有者 宗数法人慶運寺
所在地 神奈川区神奈川本町18番地2
登録資料
本尊浦島観世音(旧観福寿寺蔵)1躯
浦島父子搭(旧観福寿寺蔵)1基
浦島寺碑(旧観福寿寺蔵)1基
所有者 宗数法人蓮法寺
所在地 神奈川区七島町21番地
登録資料
伝供養塔 3基
顕彰歌碑 太田唯助作 1基
横浜市神奈川区にも伝わる浦島太郎伝説は、観福寿寺に伝えられていた緑起書に由来すると考えられますが、同寺は慶応4年(1868)に焼失したため、縁起の詳細については確認できません。しかし、『江戸名所図会』『全川砂子』などの文献には縁起に関する記述がみられます。
それらによると、相州三浦の住人浦島太夫が丹後国(現在の京都府北部)に移住した後、太郎が生まれた。太郎が20歳余りの頃、澄の江の浦から龍宮にいたり、そこで暮らすこととなった。3年の後、澄の江の浦へ帰ってみると、里人に知る人もなく、やむなく本国の相州へ下り父母を訪ねたところ、300余年前に死去しており、武蔵国白幡の峯に葬られたことを知る。これに落胆した太郎は、神奈川の浜辺より亀に乗って龍宮へ戻り、再び帰ることはなかった。
そこで人々は神体をつくり満島大明神として祀った、という内容です。
この浦島伝説が伝わっていた観福寿寺の資料は、同寺とゆかりの深い慶運寺(本寺)と、大正末期に親福寿寺が所在した地に移転してきた蓮法寺(神奈川区七島町21番地)に残されています。
慶運寺に移された浦島観世音は、浦島太郎が龍宮から玉手箱とともに持ち帰ったとされるもので、亀の形をした台座の上に「浦島寺」と刻まれた浦島寺碑や浦島父子塔とともに、浦島伝説を今日に伝えるものです。
横浜市教育委員会
パブリックアート散歩 - Google マイマップ
ブログ用地図


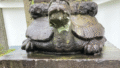
コメント