
| タイトル | 法政大学発祥の地 |
| 作者 | 不明 |
| 設置場所 | 東京都千代田区 杏雲堂病院前 |
| 製作年 | 2011 |
| 発祥年 | 1880〜 |
下記のように記されている。
法攻大学発祥の地
法政大学の前身である東京法学社は、1880(明治13)年4月、旧駿河台北甲賀町19番地池田坂上(現在、千代田区神田駿河台一丁目8番13)に設立されました。
翌年5月、東京法学社の講法局が独立して東京法学校となり、その開校とともに日本近代法の礎を築いたフランス人法学者ボアンナード博士による講義が始まりました。
その後、和仏法律学校を経て、1903年8月、法政大学と改称されました。
2011(平成23)年5月、建立
法政大学の創始者の一人である金丸鉄(まがね)は、1852年に現在の大分県、杵築藩の藩士の子どもとして生まれる。1871年(明治4年)、19歳の時に上京する。1877年に、時習社を創立し、社長兼編集者として同年「法律雑誌」を創刊した。「法律雑誌」は、日本初の法律専門雑誌である。金丸が、自らの手で進路を切り拓くことができた背景には、杵築の藩校、私塾で「素読・講義・会読」を重ね、読解や議論の能力を培っていたこと、藩校でフランス語をすでに学んでいたことがある。また、この1880年は自由民権運動が大いに流行した年で、日本国内に2,000もの結社が作られたという時代の流れも後押しとなった。
金丸は同郷の先輩で浅草に私塾・法律学舎を開いていた元田直と親交を結び、元田の下にいた代言人で杵築藩出身1855年生まれの伊藤修、1956年京都生まれで司法省雇、民法編纂局勤務だった薩埵正邦と3人を中心に東京法学社を設立した。3人とも20代の青年だった。
この土地は、幕末における攘夷派の公家で維新後は参与も務めた大原重徳の私邸の一角。東京大学を擁する本郷と、政権中枢が置かれた霞ヶ関の間にあたる神田界隈には、当時、多くの私学専門学校が生まれた。
パブリックアート散歩 - Google マイマップ
ブログ用地図

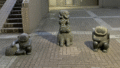
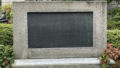
コメント