
| タイトル | 電機学校発祥の地、東京電機大学発祥の地 |
| 作者 | 不明 |
| 設置場所 | 東京都千代田区 神田スクエア |
| 製作年 | 2020 |
| 発祥年 | 1907〜(電機学校) 1947〜(東京電機大学) |
東京電機大学は、1907年に廣田精一・扇本真吉の2人の青年により設立された。
廣田は1871年広島県生まれ。1896年東京帝国大学工科大学卒業。高田商会に在籍のままドイツのシーメンス・ウント・ハルスケ電気会社入社、その後欧米諸国を視察して帰国した。
扇本は1875年岐阜県生まれ。1902年に東京帝国大学工科大学卒業し、シーメンス・ウント・ハルスケ電気会社、深川電燈株式会社、江ノ島電気鉄道株式会社などに勤務。
2人は、日本で高度な先端技術を教える学校が少ないことを危惧し、若い開発者が工業技術を学ぶことのできる学び舎として、1907年に共同して電機学校を設立した。働きながら学ぶ者のため、初めは夜間学校だった。初代校長は扇本。
1914年に、廣田が中心となり、学校の付帯事業として電気工学の専門雑誌「OHM」を創刊。誌名は、「オームの法則」のオームと、校長・扇本真吉(O)、廣田精一(H)、教頭・丸山莠三(M)の頭文字をかけたとの説がある。廣田は、現、神戸大学工学部設立にも創立者として参画した。
電気学校は、1924年12月に日本で初めてとなるラジオ放送を開始。NHKが実験放送したのは遅れて翌1925年3月だった。1928年には高柳健二郎による日本初のテレビの公開実験放送も電機学校で行われた。1949年に東京電機大学となる。初代学長はファクスの発明者でもある丹羽保次郎で、日本の10大発明家の1人と呼ばれる人物。電気学校の理念は、現在も脈々と未来の世代に引き継がれている。
秋葉原電気街の成り立ちは、一説によると、近隣にあった電機学校の関係者に向けて部品や機材の販売店が軒を連ねたからと言われている。
パブリックアート散歩 - Google マイマップ
ブログ用地図

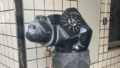
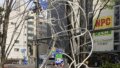
コメント