
| タイトル | こけし |
| 作者 | 不明 |
| 設置場所 | 仙台市青葉区 JR仙台駅 |
こけしは東北地方発祥の木の人形。江戸時代後期に、温泉宿の土産物などとして、木の端材など使ってろくろで作られた。主に12系統に分類される。青森の津軽系、岩手の南部系、秋田の木地山系、宮城は鳴子系、作並系、遠刈田系、弥治郎系の4系統、山形は肘折系、山形系、蔵王高原系の3系統、福島は土湯系と中ノ沢系の2系統。系統ごとの個性が楽しい。
宮城県の遠刈田温泉で作られている遠刈田系は確認されているこけしの史実の中で発生年代が最も古く、こけし発祥の系統とされる。その特徴は極めて大きい頭部と細い胴体、そして、頭部を華やかに彩る放射状の赤い手絡(または黒いおかっぱ)である。この陳列の向かって一番右のこけしがその特徴を備えている。
弥治郎系も宮城県のこけし系統の一つで、ベレー帽のような頭部の模様と胴体のくびれが特徴。温泉の湯治客の要望を入れて製作したので、バラエティに富んでいるといわれる。真ん中と左端は弥治郎系だと思われる。
作並温泉も一説によるとこけし発祥地といわれる。作並系は、小さな頭と細い胴体、「かに菊」と呼ばれる胴体の独特の模様が特徴。中央の弥治郎系を挟んだ両脇の2体が作並系ではないか。端正なこけしだ。
鳴子系は、頭を回すとキイキイと音がするのが最大の特徴。瓜実型の頭部、前髪・髷が描かれ、頭頂部の水引で髪を止めるのがスタンダード。胴体は安定感のある形状。作並系の脇の最も大きな2体が鳴子系ではないか。
なお、肘折系はもともと山形発祥のこけしだが、明治期に肘折から仙台に移住した佐藤周助から始まり、鳴子系や遠刈田系の要素がミックスされ宮城県の伝統こけしの系統の一つになった。宮城県の伝統こけしは肘折系を含め5系統ということになる。肘折系は胴は太く直胴で肩が張り、顔は目鼻立ちがはっきりし、髪は黒々としたおかっぱ。向かって右手前の小さい2体は肘折系だろうか。
あくまで素人の当てずっぽうなので、間違ってたらすみません。推理できる範囲で考えてみました。作家ごとの違いもあるし、コレクションするとかなり楽しそう。


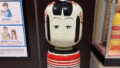
コメント